
[卓球本悦楽主義23] 卓球讃歌、コンプレックス、近親憎悪。共感を呼ぶ骨太の卓球本
〈卓球専門書の愉しい読み方23〉卓球王国2005年11月号掲載
『ピン本 極楽卓球のススメ』
■ 立川竜介・著[平成十二年 総和社]

卓球讃歌、コンプレックス、近親憎悪。共感を呼ぶ骨太の卓球本
初めてこの本を見たとき、私は極めて強いマイナスの興味を抱いた。「立川竜介」という、落語家と漫才師をまぜたような著者名と、軽薄なタイトル。卓球をろくに知らないライターが聞きかじりの情報をもとに書いた、底の浅い卓球ブーム便乗本に違いない、と思ったのである。確かめてやろうと読んでみると、そうではなかった。
著者は雑誌などで連載を持ち、単行本もいくつか出している文筆家だが、8歳から高校1年まで、しっかりと卓球をやっていたのである。著者が中学生の頃、ある事件が卓球界を襲う。
その当時、ラジオの深夜放送「オールナイトニッポン」のパーソナリティーとして、深夜族に大きな影響力を持っていたタモリさんが、世の中に送り出した代表的な流行語が「ネアカ」と「ネクラ」。卓球は「ネクラ」の代名詞となり「卓球ほどネクラなものはない」「卓球をやっている人間はネクラの象徴だ」という認識が、流行という次元をあっさりと飛び越えて、一般常識になった。
津波のように押し寄せてきた「ネクラ」の猛威に、立ちすくむばかりの卓球部員は、一瞬にして飲み込まれた。
80年代初めに日本の卓球界を襲った「卓球は暗い」ブーム。それは経験した者にしかわからない屈辱(くつじょく)だった。初対面の相手にさえ「卓球? 暗いね」とお約束のギャグとして言われた時代。本書は、その暗黒時代の真っただ中を地区予選どまりの無名の選手としてすごした著者が、自嘲(じちょう)的にユーモラスに同世代の隠れ卓球経験者へ共感を呼びかけつつ、一般人にも卓球の魅力を語る、骨太(ほねぶと)の卓球本だったのである。
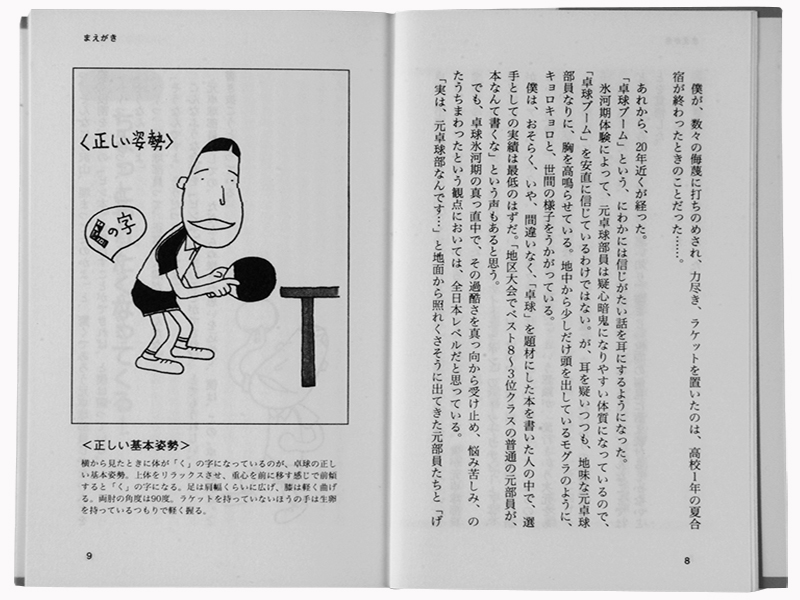
著者は卓球をやめた今でも、選手時代に受けた屈辱を忘れることができない。テレビで昨今の卓球ブームについて語る同世代のアナウンサーの目には”冷ややかな光”を感じるし、雑誌の見出し「卓球ブーム!?」の?マークにも揶揄(やゆ)を読み取る。マンガ「行け! 稲中卓球部」がヒットしたときの著者の反応は次のようなものだった(結局は誤解だったのだが)。
漫画を多読している友人から「稲中はスポ根漫画じゃなくて、ギャグマンガ」だと聞かされた僕の思考は、一つの方向性で凝り固まった。
この漫画は、卓球及び卓球部員を笑い者にする漫画に違いない。
そうだ。そうに違いない。
著者は異常なのだろうか。そうではない。私もまったく同じなのだ。多感な時期にあの暗黒時代を経験した者なら、誰でもこうなってしまうのではないだろうか。
著者の卓球に対する思いは複雑である。卓球を愛しながらも、近親憎悪(ぞうお)のような気持ちも抱く。
卓球界には美男美女が少ないとし、その理由は、彼らが卓球を見たとき「これは自分がやるべきスポーツではない」と直感するからだという。同様に、運動神経の良いヤツは「自分が卓球をするなんてもったいない」という気持ちを持つ、とも書く。
残念ながら、私は、著者のこの考えを100%否定することはできない。現実に日本ではその傾向があると思う。卓球競技のサイズの小ささ、ゲーム性、技巧性がそのような印象を与えるのだろう。
前原正浩(元日本代表)は現役時代、選手生命を賭けて転向した異質反転型を短期間でマスターするために、食事中も左手で箸を使い、右手でラケットの反転操作の練習を続けたという。ステラン・ベンクソン(71年世界チャンピオン)は、第1回ワールドカップで、卓球台の中央が1cm弱高いのを見抜き、脚を切らせて試合をした。
卓球とはこういうスポーツなのである。こういう人たちがチャンピオンになるスポーツなのである。明るさ・爽やかさ・力強さ、よりは、複雑・緻密・執念のスポーツなのだ。

著者は部外者という強みを活(い)かし、卓球関係者には書けないことを書く。卓球の暗いイメージを払拭(ふっしょく)しようとして日本卓球協会が企画したイベント「ザ・卓球」を”卓球夜明け前、痛恨のディナーショー”と題してコケにする。また、著者が少年時代、卓球の一流選手に憧れることができなかったのは、彼らの「顔」のせいだと書く。
なぜかと言えば、長谷川選手はウチの近所の八百屋のオヤジにソックリだったし、高島選手は魚に似ていたし、黒ブチ眼鏡をかけていた前原選手は役所の窓口に必ずいる生真面目そうなタイプだったし、小野選手はコソ泥みたいな顔をしていたからだ。
私は「こんなことを書いていいのか?」と思いながらも、読みながら思わず吹き出してしまった。思えば、卓球雑誌に出てくるギャグに笑ったことなどない。卓球がメジャースポーツになるためには、こういう種類の笑いも許容する幅が必要なのではないだろうか(それにしても、世界チャンピオンをつかまえて”コソ泥”とは)。

本書の最後に、著者が正月に帰省したときに、中学時代のライバルだったM君の新築の家に招かれた話が出てくる。
そして数時間後、「悪いんだけど、今日中に東京に戻らなくちゃ……」と、腰を上げようとした僕に、Mが言った。真剣な目になって言った。
「あと30分くらいはいいだろ?」
そう言われて、M邸のガレージに連れられていくと、そこに、卓球台があった。
「どうや、ちょっとやろまいか」
ここで著者は15年ぶりにラケットを握り、卓球に対するさまざまな想いを巡らせながら旧友とラリーを続ける。それは、著者自身が書くように、映画『フィールド・オブ・ドリームス』を思わせる少しだけ感動的な場面であり、卓球賛歌とコンプレックスと近親憎悪に満ちたこの本の最後を締めくくるのに相応(ふさわ)しいものであった。(文中敬称略)
*太字は原文から引用してそのまま掲載
■Profile いとう・じょうた
1964年岩手県生まれ。中学1年からペン表ソフトで卓球を始め、高校時代に男子シングルスで県ベスト8。大学時代、村上力氏に影響を受け裏ソフト+アンチのペン異質反転ロビング型に転向しさんざんな目に遭う。家電メーカーに就職後、ワルドナーにあこがれシェークに転向するが、5年かけてもドライブができず断念し両面表ソフトとなる。このころから情熱が余りはじめ卓球本を収集したり卓球協会や卓球雑誌に手紙を送りつけたりするようになる。卓球本収集がきっかけで2004年から月刊誌『卓球王国』でコラムの執筆を開始。世界選手権の[裏]現地リポート、DVD『ザ・ファイナル』の監督なども担当。中学生の指導をする都合から再びシェーク裏裏となり少しずつドライブができるようになる。2017年末に家電メーカーを退職し卓球普及活動にいそしむ。著書に『ようこそ卓球地獄へ』『卓球天国の扉』がある。仙台市在住。







![[卓球本悦楽主義1] 過剰なまでに論理的な荻村の語り口に圧倒された](https://plus.world-tt.com/wp-content/uploads/2023/09/卓球世界のプレー-150x150.jpg)
![[卓球本悦楽主義6] 「スロー、スロー、クイック、クイック」感覚的な独特の打球論が展開。](https://plus.world-tt.com/wp-content/uploads/2024/06/アイキャッチ-1-150x150.jpg)
![[卓球本悦楽主義17] 当時の雰囲気を味わえる記事、卓球メジャー化への情熱が胸に迫る](https://plus.world-tt.com/wp-content/uploads/2024/07/アイキャッチ-5-300x300.jpg)
![[卓球本悦楽主義19] 理論家・福士により蘇る昭和初期以前の技術と選手](https://plus.world-tt.com/wp-content/uploads/2024/09/アイキャッチ-300x300.jpg)
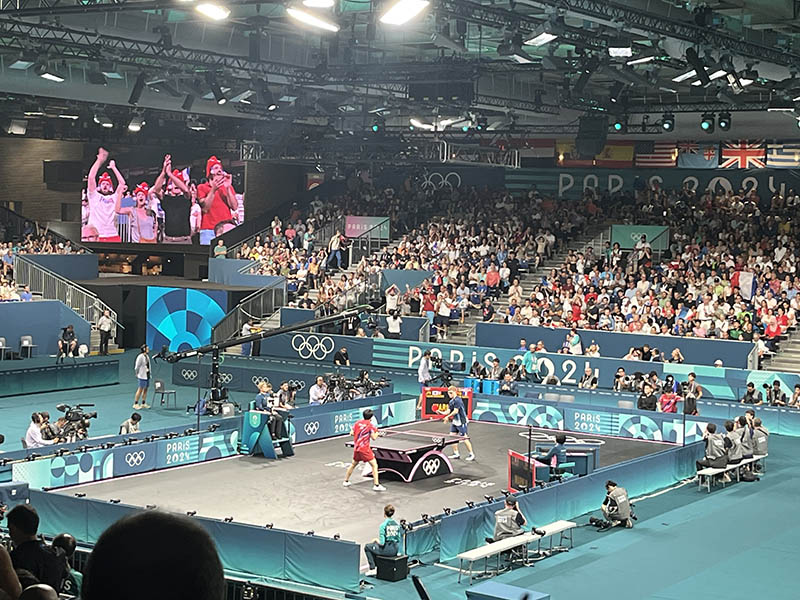

![[プロコーチの草分け、37年目の挑戦]村上恭和「最後の仕事として、このピラミッドを形にしたい。死ぬまでにね」](https://plus.world-tt.com/wp-content/uploads/2026/02/ロンドン村上7543-1.jpg)


![[卓球本悦楽主義9] 意気盛んな荻村の濃密な理論が展開。まさに卓球理論書の金字塔](https://plus.world-tt.com/wp-content/uploads/2024/06/アイキャッチ-3-300x300.jpg)
