
[アーカイブ徐寅生の独白]「一時的に最先端の技術であっても、発展を続けない限り必ず時代遅れになり、最終的には淘汰されてしまうのです」
卓球王国2010年2月号より Vol.2
中国は何事もなく、順調に世界の王座にたどり着いたわけではない。60年代には文化大革命という権力闘争によって卓球人もつらい時を過ごし、僚友を失いもした。負の時間を経て、いかに盤石の王国を作り上げたのか。
中国卓球史の証人――徐寅生。変革の嵐の中で、中国卓球の歴史の裏も表も見てきたカリスマが、その過去を語る。

Interview by
翻訳=偉関絹子・謝静・柳澤太朗
写真=高橋和幸 協力=ピンポン世界
徐寅生/シュ・インション(ジョ・インセイ)
1938年5月12日生まれ、上海市出身。8人兄弟の末っ子として生まれる。戦型は右ペンホルダー表ソフト速攻型。上海光大中学在籍時の55年に上海学生チーム、翌年に上海市チーム入り。59年には国家チームに入り、同年の世界選手権ドルトムント大会に初出場。61年の第26回世界卓球選手権では、男子団体の主力選手として、中国男子の団体初優勝に貢献。世界選手権には65年のリュブリアナ大会まで4大会連続で出場。男子団体で3個、男子ダブルスで1つの計4個の金メダルを獲得。そのクレバーな戦いぶりで「智多星」と賞賛された。1977年に国家体育運動委員会(現在の国家体育総局)副主任=スポーツ副大臣に就任、79年に中国卓球協会の第二代会長となり、30年にわたり中国卓球界のトップとして活躍。95年にはロロ・ハマランドの後を継いで第五代国際卓球連盟会長となる(99年に退任)。09年に中国卓球協会会長を退任し、同名誉会長に就任

「ひとつの打法、ひとつのスタイルは一時的に最先端の技術であっても、発展を続けない限り必ず時代遅れになり、最終的には淘汰されてしまうのです」
61年北京大会の私たちの優勝は、中国全土で大きな反響を呼びました。中国が初めて世界選手権で優勝したのですから
かつて荻村伊智朗(故人・元国際卓球連盟会長・世界チャンピオン)が自身の著書の中で、「同じアジア人で、同じような体つきの日本人が世界で勝てるなら、自分たちも勝てるはずだと中国は考えたのではないか。混乱した国内情勢の中で、世界で勝つために卓球に力を入れていたのではないか」と記述している。建国間もなく、国威発揚のために卓球というスポーツが選ばれ、成果をあげて、まさしく中国人民に力を与えた。ゆえに卓球は「国球」となり、政治的なスポーツとして国に育てられ、注目を集めていく。
◇◇
徐寅生 卓球は中国人を含むアジア人に適したスポーツだと思います。アジアの選手は比較的動きが敏捷であり、体もヨーロッパ選手より柔らかい。そしてヨーロッパ選手に比べて体格で劣るアジア選手にとって、卓球には身体の接触がないことも重要な要素です。
また、60年代当時、アジアの選手はペンが主流で、ヨーロッパではシェークが主流だった。少数派であるペンホルダーは多数派のシェークに適応しやすく、逆にヨーロッパのシェークはペンホルダーの選手が少ないため、なかなか対応できなかったと言えるでしょう。敏捷さと頭の回転の早さを生かして、アジアはヨーロッパより多彩な卓球ができた。


 卓球王国PLUS有料会員になると続きをお読みいただけます
卓球王国PLUS有料会員になると続きをお読みいただけます

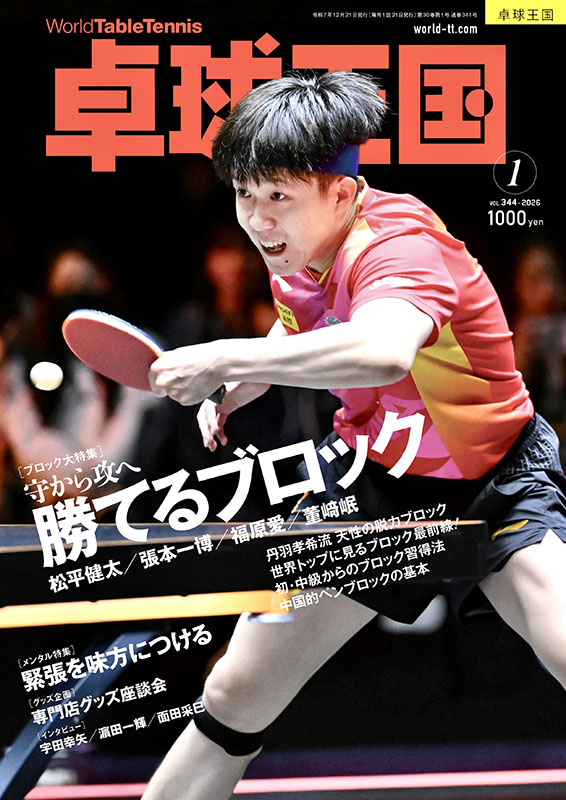
![[アーカイブ徐寅生の独白]カリスマ指導者が語る中国卓球史。最強の中国卓球はいかに作られたのか](https://plus.world-tt.com/wp-content/uploads/2025/04/徐寅生P9831-1-300x300.jpg)
![[馬龍・アーカイブ特集その2]「ぼくは逃げ道を作らなかった。戦いの場から逃げるくらいなら自分のことを信じよう」](https://plus.world-tt.com/wp-content/uploads/2024/10/アイ馬龍フォア飛びつき-300x300.jpg)
![[アーカイブ・女王の独白/前編]丁寧「自分だけが狙っているわけじゃないから、苦しい試合が連続してあるのも当たり前」](https://plus.world-tt.com/wp-content/uploads/2024/10/アイキャッチ丁寧扉-300x300.jpg)
![[馬龍・アーカイブ特集その3]王者の独白・馬龍、語る。「どん底に落ちたけど、這い上がってきた」](https://plus.world-tt.com/wp-content/uploads/2024/10/キャッチ馬龍とびら-300x300.jpg)
![[2019年全日本プレイバック]7年前の男子ランキングプレーヤー](https://plus.world-tt.com/wp-content/uploads/2026/01/水谷-1.jpg)
![神のサービス[仲村錦治郎]ナックルを習得する!](https://plus.world-tt.com/wp-content/uploads/2025/12/7神のサービス1月号修正済-1.jpg)

![[People]今 佳恵「情報提供や対応は常に平等であることを心がけています」](https://plus.world-tt.com/wp-content/uploads/2025/12/あいこん9398.jpg)

![[アーカイブ徐寅生の独白]私たちは「前進なきは後退」という言葉を失敗から学んだ](https://plus.world-tt.com/wp-content/uploads/2025/04/徐9838-1-300x300.jpg)
![[ワルドナー伝説]vol.21 第3章 4 ワルドナー卓球の真髄](https://plus.world-tt.com/wp-content/uploads/2024/12/1996_わるどなーSV-のコピー-300x300.jpg)
![[ワルドナー伝説]vol.22 第3章 5 予測不可能なワルドナー](https://plus.world-tt.com/wp-content/uploads/2024/12/ワルドナー_バック-300x300.jpg)