
全国中高優勝・野田学園の橋津文彦監督「我慢しないこと」を教え、「我慢すること」を教える
卓球王国PLUS独占記事

日本一の子には「我慢しないこと」を教えて、予選落ちの子には「我慢すること」を教える
ぼくは24歳から高校の指導を始め、野田学園で指導をはじめて16回目のインターハイでようやく優勝することができました。
27年間で変わったのは、子どもたちの気質です。(岸川)聖也(現・全日本男子監督/世界メダリスト)の頃は、ぼくは兄貴分のような感覚でしたが、今では選手たちの親より年上になり、自分の経験を話しても「響いていないかも」と思うことがあります。
同じ話を繰り返しているうちに、「先生、また同じ話をしているよ」と思っていた子どもの頃の自分を思い出し、今は自分が同じことをしているのかもしれないと感じることもあります。
昔は、強い選手の体験談や自分の経験を語って「さあ、みんなで優勝を目指そう!」とチーム全体で突き進むような指導をしていました。しかし、今はそれが通用しない時代です。
チームの中には日本一の選手もいれば、予選落ちする選手もいます。だから、日本一の子には「我慢しないこと」を教え、予選落ちの子には「我慢すること」を教えています。つまり、同じチーム内でも真逆のことを言うことがあるのです。
もちろん、チームとしての規律や統制も必要です。しかし個々の選手には、「おまえは我慢しなくてもいい」と言うこともあれば、「我慢しないと強くなれないぞ」と言うこともあります。
「我慢しろ」と言う言葉にも、教育としての意図や愛情があります。ただ、それが子どもには理解されにくいことも多い。しかし、我慢してきた子は社会に出た時、「我慢しなかった子」より早く自立していくように感じます。
一方、「我慢するな」と言った子は、そのまま突き進んでチャンピオンになったり、世界選手権に出たりもします。

勝てば「伸び伸びしている」と言われ、負ければ「だらしない」と言われる
うちのチーム(野田学園)は、勝った時には「伸び伸びしている」と言われ、負けた時には「だらしない」と言われます。そういう意味で、野田学園は決まったおかずの「定食」ではなく、アラカルトの個別メニューを出す食堂のようなチームです。
Aには厳しく、隣のBは褒めて、その横のCはおだてる。20人いれば20通りの対応があります。
ぼく自身が「昔のあの選手はこうだった」と話すよりも、なるべく当人に来てもらって直接話してもらうことで、選手たちにいろんな考え方を知ってもらうようにしています。そうした上で、チームがひとつにまとまるような指導に変えてきました。
最近とくに感じるのは、コロナ禍とその後で、子どもたちの心持ちや雰囲気が一気に変わったことです。世の中のマインドが自由になり、多様化しているように思います。
チームには日本一を目指す子もいれば、予選落ちした子もいる。その中でチームをまとめることは、これまで以上に難しくなっています。
この変化の背景には、SNSの急速な普及もあるでしょう。今の子どもたちはスマホを常に手にしていて、50代のぼくらには理解しづらい世界で生きています。だから、昔の自分の経験をそのまま当てはめても通用しない。「何言ってんだ、このおっさん」と思われているかもしれません。
子どもたちだけでなく、親御さんの意識も変わってきています。これからはますますその傾向が強くなるでしょう。
自分の信念や卓球への思いは変わらなくても、教える相手と世の中は急激に変化しています。その中で、自分の言葉をどう伝えていくか──いまも模索を続けています。
[はしづ・ふみひこ]
1974年5月10日生まれ、山口県出身。柳井商業高3年時に中国高校選手権3冠を達成。1年間のドイツ卓球留学を経て明治大に進学。卒業後、東洋大姫路高を経て仙台育英学園高の教員・卓球部監督となり、03・04年インターハイ学校対抗で優勝。
野田学園(山口)監督として2025年のインターハイ学校対抗で初優勝。全国中学校大会では総監督として団体優勝に導いた。




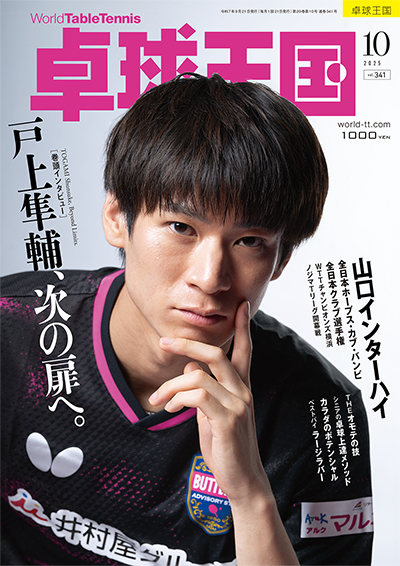








![[こだわりすぎた男たち 河西守]両面粘着ギアは驚愕の221g。回転の幅でラリーを制す](https://plus.world-tt.com/wp-content/uploads/2025/10/wanishik-1.jpg)



